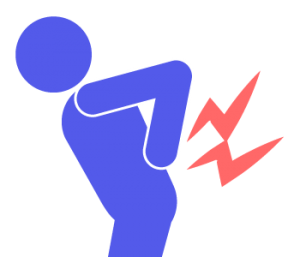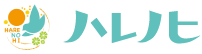こんにちは。
ハレノヒの有水です。
今回は春先に起こる腰痛の原因と対策についてお話します。
春先は寒暖差が大きく、自律神経の乱れや筋肉の硬直が原因で腰痛が悪化しやすい季節です。また、新生活による環境の変化や花粉症の影響なども、腰への負担を増やす要因になります。ここでは、春先の腰痛の主な原因と対策について詳しく解説します。
【春先に腰痛が起こりやすい主な原因】
① 気温の変化による筋肉の緊張
春は昼夜の気温差が大きく、寒い朝晩には筋肉が硬直しやすくなります。筋肉が硬くなると血流が悪化し、腰痛が引き起こされやすくなります。
② 自律神経の乱れ
春は気圧の変化が大きく、交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすい季節です。自律神経の乱れは筋肉の緊張を引き起こし、腰痛につながることがあります。
③ 花粉症による影響
花粉症の症状がひどい人は、くしゃみや咳が増えます。これにより、腹筋や背中の筋肉が繰り返し緊張し、腰に負担がかかります。また、鼻づまりによって姿勢が悪くなり、腰痛を引き起こすこともあります。
④ 新生活によるストレス
春は入学や就職、引っ越しなど環境の変化が多い時期です。ストレスが溜まると筋肉が緊張し、腰痛の原因になることがあります。
⑤ 運動不足と急な活動再開
冬の間に運動不足になっていた人が、春先に急に運動を再開すると、筋肉や関節に負担がかかり腰痛を引き起こすことがあります。
【春先の腰痛を予防・改善する方法】
① 体を温める
朝晩は特に冷えやすいため、腰を冷やさないように 腹巻やカイロ を活用する。
入浴時に 湯船に浸かる ことで筋肉を温め、血行を促進する。
② 適度なストレッチを行う
腰痛を防ぐためには、 股関節や背中の柔軟性を高めるストレッチ が効果的です。
キャット&カウストレッチ(背中を丸めたり反らせたりする)
骨盤の前後傾ストレッチ(腰の動きをスムーズにする)
ハムストリングスのストレッチ(太ももの裏の柔軟性を高め、腰への負担を減らす)
③ 自律神経を整える
深呼吸 や リラックスできる時間 を作り、自律神経のバランスを整える。
朝日を浴びて生活リズムを整える。
④ 花粉症対策
花粉症が原因で姿勢が悪くなる場合は、こまめに鼻をかむ、マスクを使用する などの対策を取る。
くしゃみや咳が続くときは、 体幹を意識して支える筋肉(腹筋や背筋)を鍛える ことも有効。
⑤ 適度な運動
ウォーキング や 軽い筋トレ などを日常的に取り入れ、腰回りの筋肉を強化する。
冬の間に運動不足だった人は、急に激しい運動をせず、徐々に運動量を増やす ことが大切。
【春先の腰痛に効果的なツボ】
腰痛を和らげるために、鍼灸や指圧でツボを刺激するのも効果的です。
① 委中(いちゅう)
場所:膝の裏の中央
効果:腰痛や坐骨神経痛を和らげる
刺激方法:膝を軽く曲げて、親指でゆっくり押す
② 腎兪(じんゆ)
場所:腰の高さで背骨の両側、指2本分外側
効果:腰の血流改善、腎の機能を高める
刺激方法:手のひらで温めながらゆっくりマッサージ
③ 太谿(たいけい)
場所:内くるぶしとアキレス腱の間
効果:冷えによる腰痛や腎の不調を改善
刺激方法:温灸やお風呂で温めると効果的
【まとめ】
春先の腰痛は、 寒暖差、自律神経の乱れ、花粉症、ストレス、運動不足 などが主な原因です。予防と対策として、体を温める、ストレッチを行う、適度に運動する、自律神経を整える ことが大切です。
また、 委中・腎兪・太谿 などのツボを刺激すると、腰痛の緩和に役立ちます。春の不調を防ぎ、快適に過ごせるように、日々のケアを心がけましょう!
※イラストはAIで作成しました。
椎間板ヘルニア
ライフスタイル(仕事や趣味)または年齢による体の変化、スポーツなどによる負荷がきっかけで、背骨の間には椎間板という衝撃をやわらげるクッションの中央にゼラチン状のやわらかい髄核があります。原因は、腰を曲げた時などに椎間板の内圧が上昇しその髄核が押し出されることで神経根を圧迫し、腰の痛みや足のしびれを引き起こします。
軽度の場合は姿勢や動作に気をつければ自然に治ることもありますが手術が必要なこともあります。
■椎間板ヘルニアには、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎椎間板ヘルニアなどがあります。
■症状
・座骨神経痛(腰と足の痛みやしびれ)
・動きの中での痛み。特に座ったり、中腰姿勢で痛む
・慢性化しやすい。
・安静時でも痛くなる。

椎間板ヘルニアが慢性化してしまったら(慢性腰痛)
慢性腰痛、下肢のしびれ、何ヶ月・何年も痛い腰痛などは温めると痛みが緩和します。ただし、患部に打撲や外傷があったり、または熱を持っている時は温めないでください。
温める時の注意と方法
冷やす時とは違い長い時間(1回30分程度)温めることは可能ですが火傷(低温火傷)にはご注意下さい。薬局などで湯たんぽのジェル用が販売されています。ジェル用湯たんぽは整形外科などにあるホットパック(患部を温める医療用具)の代用になります。
急性腰痛症(ぎっくり腰・ギックリ腰)
急性腰痛は通称ぎっくり腰と言われドイツ語では「魔女の一撃」とも呼ばれます。なんの前ぶれまなく突然「ギック」と痛みが襲います。発症すると腰を曲げられなくなる、また伸ばせなくなる、寝返りが痛む、歩行も痛みで困難、靴下を履けないなどの症状がみられます。
ぎっくり腰はいわゆる腰椎捻挫です。腰の骨のかみ合わせがズレたり筋肉の炎症など原因で起こります。またそれ以外でも様々ですが予期せぬ腰痛なだけに、治っても再発するす方が多いです。
■症状
・突然痛みが出て動けなくなる
・腰に力が入らない
・動くと激痛
・腰の炎症

ぎっくり腰など急に生じた腰痛(急性腰痛)
冷やすことで痛みを和らげることができます。ただし、痛みが増すような場合は中止してください。また、長時間の冷やし過ぎは凍傷の危険性や腰痛の回復を遅らせるおそれがあるので、注意してください。
冷やす時の注意と方法
15分患部を冷やしたら15分休憩して下さい。休憩後また15分冷やして15分休憩です。それを3セット繰り返して終了です。
※冷やしすぎると凍傷の危険性があるのでご注意下さい。
《腰痛の種類》
・いわゆる腰痛症(骨や椎間板には問題がない)
・急性腰痛(ぎっくり腰・ギックリ腰)
・椎間板ヘルニア
・筋筋膜性腰椎
・座骨神経痛
・腰部脊柱管狭窄症
・変形性腰椎症
・腰椎分離症、すべり症
・骨粗鬆症
●当治療院で施術可能な症状です。
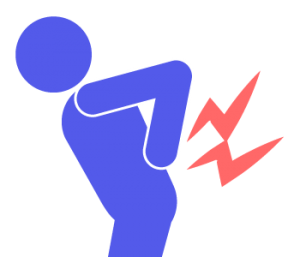
◆腰痛症になりやすい人とは◆
基本的にはその方のライフスタイル(仕事や家事、私生活)にあります。学生であればスポーツをやってる方が圧倒的に多いです。
腰痛になる原因はさまざまですが、なりやすい人には少し共通点があります。
・体がかたい人(筋肉が緊張しやすく、血行が悪くなりやすい)
・姿勢や歩き方が悪い人
・運動不足、筋力不足の人
・同じ姿勢で長時間仕事や家事をする人
・重労働や運動のしすぎで筋肉疲労がある人
・柔らかいベッドで寝てる人(柔らか過ぎると腰の部分が沈んで負担がかかる)
・神経質な人(痛みを感じやすい)
◆腰痛にならないための注意とは?◆
腰に負担を掛けないために動くときは出来るだけ姿勢の良い動き方することを心掛ける。また人は二本足で歩きます。歩き方が悪いと腰痛の原因にもあります。
・姿勢や歩き方に気をつける。
・イスに座るときは足を組んだり、猫背姿勢にならない。(パソコン時の姿勢)
・重い物を持つ時は「前かがみ」ではなく、しゃがんで腰を伸ばし、下半身の力を使って持ち上げるなどの工夫が必要。
・間違った靴、スニーカーを履いている。(クロックスやスリッパは履かない)
・体を冷やさない。
・規則正しい生活に心掛ける。(しっかりとした睡眠など)
・自分の体を理解すること。
・ストレスを溜めないこと。
◆腰痛になってしまった時◆
それでも腰痛になってしまったら、どうしたらよいか?
治療院や病院・接骨院などでの治療も大事になりますが、当治療院で最も大切なことはセルフケアをしっかりやっていただく事だと考えています。
【セルフケア】
◎ストレッチ
腰周りのストレッチはとても重要なことになります。それにくわえ全身のストレッチを行うことでより腰痛改善が期待できます。
◎筋力トレーニング
いわゆる腰周りの筋力強化です。特に重要なポイントは体幹トレーニング(アウターマッスル、特にインナーマッスル)を行うと効果があがります。
◎寝るとき腰に負担のかかる姿勢を避ける
・横向き ・・・ 腰をくの字にして寝る。
・うつ伏せ ・・・ お腹の下に座布団を入れて寝る。
・仰向け ・・・ 足の下に座布団を入れて寝る。
◎サポーターやテーピング
薬局などで自分判断し購入せず治療院や接骨院などの先生に相談しその方に合ったサポーター使用したり、テーピングなどは張り方などの指導を受けてやることが効果的になります。間違ったサポーターやテーピングをすることで腰痛が悪化する場合もあります。お気を付け下さい。
◎ぎっくり腰など急に生じた腰痛(急性腰痛)
冷やすことで痛みを和らげることができます。ただし、痛みが増すような場合は中止してください。また、長時間の冷やし過ぎは凍傷の危険性や腰痛の回復を遅らせるおそれがあるので、注意してください。
《冷やす時の注意と方法》
ビニール袋に氷と塩をひとつまみ入れ、タオルをはさんで腰にあてる方法と市販のアイスパックなどでタオルをはさんでから腰にあてる方法などで15分患部を冷やしたら15分休憩して下さい。休憩後また15分冷やして15分休憩です。それを3セット繰り返して終了です。
※冷やしすぎると凍傷の危険性があるのでご注意下さい。
◎何ヶ月、何年も痛い腰痛(慢性腰痛)
徐々に痛くなってくる慢性腰痛、下肢のしびれ、何ヶ月・何年も痛い腰痛などは温めると痛みが緩和します。ただし、患部に打撲や外傷があったり、または熱を持っている時は温めないでください。
《温める時の注意と方法》
冷やす時とは違い長い時間(1回30分程度)温めることは可能ですが火傷(低温火傷)にはご注意下さい。薬局などで湯たんぽのジェル用が販売されています。ジェル用湯たんぽは整形外科などにあるホットパック(患部を温める医療用具)の代用になります。